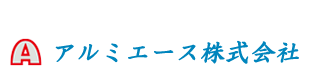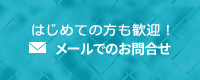2023.04.26
特殊な矯正の解説動画を公開しました。
アルミニウムの熱処理の仕事は、熱を加えるだけではありません。
「矯正」と呼ばれる、寸法を直す作業も承っています。
大きなハンマーや油圧の矯正器具も所有していますが、この動画のような精度の高い製品も扱っています。
熱処理を行わずに矯正だけの作業も承っています。
他にもバリ取りや切断も行っておりますので、お気軽にお問い合わせをいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
2023.04.19
水槽の温度管理について
アルミニウムの熱処理において、溶体化処理のときには高温から一気に急冷をすることになっております。
弊社では、水槽に水を張り急冷を行っております。
製品によっては冷却の際の水温が40℃以下という指定があったり、逆に50℃以上という場合もあります。
水温を上げるときは、ヒーターやボイラーを使用し水温を下げる場合には、水を加えてます。
水温に関しては、鍛造品は低い方が硬さが出ますし鋳物は温度が高いほうが変形が少なく割れにくいということがあります。
製品の形状や、治具への詰め方によっても最適な水温は変わってきます。
また、水温は24時間自動的に記録されております。
ご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡をいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
(記事作成 横田)
2023.04.12
ゴールデンウィークのお休みについて
弊社のお休みは、4/29(土)30(日)・5/3(水)~5/7(日)になります。
5/1・2は営業の予定になっておりますが、設備のメンテナンスなどを予定しております。また、お取引きしているお客様もお休みになる為、仕事量によっては、早上がりやお休みになる場合がございます。
お休み期間中、お急ぎでのアルミニウム熱処理や矯正作業などございましたら早めにご連絡をいただければ対応させていただきます。納品・引取りにつきましてもご要望・ご相談がございましたらご連絡をいただければ幸いです。
製品の発送につきましては、配送業者様のお休みもございますので、ご希望の納期に添えない場合がございます。宅急便での発送は出来ますので、ご連絡をいただければ対応させていただきます。
お休み期間中にいただいたお問合せやお客様からのメールにつきましては、お返事が5/8(月)以降になる場合がございます。
アルミニウム熱処理や矯正作業などのご相談がございましたらお気軽にいつでもご連絡をいただければ幸いです。宜しくお願い致します。
記事作成 (堀越)
2023.04.05
アルミ熱処理の設備点検
日々の作業を効率よく進めるために、設備や身の回りの使用する治具などを点検することも大事な仕事です。
熱処理炉に製品を入れる時に使用するバスケットの点検もあります。
熱処理炉の大きさに種類があり、それに合ったバスケットを使用するため、バスケットの形や大きさは様々です。
使用する頻度にもよりますが、回数を重ねていくとバスケットの熔接部分が脆くなっていくため、日々点検をして、異常があれば、すぐに熔接をして対処します。
弊社の設備に溶接機があるので、熔接などは社内で行います。
フォークリフトやクレーン、検査器具などの重要項目は自分たちで点検もしますが、社外に依頼して、校正を取ります。
お客様からのご質問で、設備の大きさを聞かれることが多くありますので、どのような大きさでも、すぐに対応できるように準備をしておきたいと思います。
アルミ熱処理の事でご質問等ございましたらお気軽にご連絡いたただければと思います。
宜しくお願い致します。
2023.03.29
熱処理炉と治具の寸法について その①
皆様こんにちは。
桜の花が北関東でもずいぶん開花し春が訪れたと実感する今日この頃です。
さて今回の内容は、「製品が熱処理炉に入るか知りたいので、寸法を教えてほしい」とお問い合わせが、よくありますので、
寸法について説明致します。
熱処理炉と治具の寸法について代表的な炉と治具の説明をしたいと思います。
弊社で最も使われている炉が、大型丸炉になります。
大型丸炉は気流式電気炉で、寸法は Φ1,400×H1,750mmとなります。
よくお客様から、「真空ですか?」とお問い合わせがありますが、真空炉ではなく気流式になります。
そして、この炉で熱処理を行う為には治具が必要になります。
その代表的な治具として、4段バスケットがあります。
因みに弊社では、この炉で使用する治具をバスケットと呼んでいます。
このバスケットの寸法ですが、1段の寸法Φ1,190×H400mmでこれが、4段構成になっています。
実際には治具の内径がもう少し小さくなります。
1段が約Φ1130×H300mm位の大きさです。
この他にも治具が数種類ありますので、また投稿していきたいと思います。
熱処理などで気になることが有りましたらお問い合わせ頂ければ幸いです。
(記事作成 丸山)